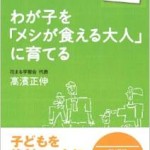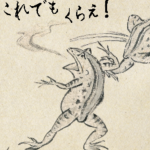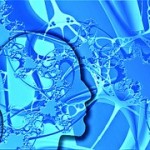2018/02/28
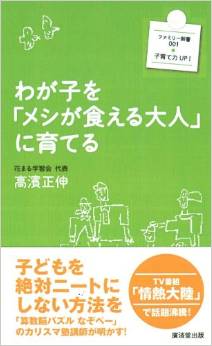
『「メシを食っていける大人」にする5つの基礎力』の1つ目に上げられている
「ことばの力」
これってやっぱり1番目にあげられているだけ重要である。
私自身この「ことばの力」が無い人間だった。
私は塾の先生をする前はバリバリのエンジニア(技術者)。
理科や数学が大好き。逆に国語や社会が苦手。
アピールが上手いやつを「口先だけのやつ!」と思ってきた。
でも、いい技術を開発してもアピールが下手だとその技術は採用されることが無く、アピール力の必要性をひしひしと感じてきた。
なんかこれって何かに似ているなと思ったら
男と女の間の「愛」と「お金」の関係だった。
一番求めているものは「愛」だけど、でも愛があっても「お金」が無きゃ暮らしていけない。
結局、女の人は「お金」を持っている男に惹かれていく・・・・
ああ、なんか寂しいけど、これが現実。
生活していく上で大事な「お金」と同じように、人とのコミュニケーション上で大事な「ことばの力」
一番苦手だったはずなんだけど、今では生徒を教えていて一番「面白い」と思うのはこの「ことばの力」
授業をするときに細かいところまで気にしなければならないので集団授業向きではないが、ちゃんと教えれば”グン!”と伸びる。
「メシが食える大人」の本の中では
①聞く力
②読む力
③話す力
④書く力
の4つに分けて説明されていたが「読む力」と「書く力」について書いてみたい。
●「読む力」
「うちの子供は本は結構読んでいるのに、何で読解問題が苦手なんだろう・・・」
と思っている家の子供は
「漫読」になっていて「精読」をしていないとこの本の中で言っている。
うちの塾でも「漫読」をしているな~っていう生徒に「精読」の練習として個別授業で文を段落ごとにまとめさせる練習をさせている。
まとめたチェックすることは簡単なことのように見えるが、まとめた文について質問して確認してみないと、上手く書けているように見えてぜんぜん理解できていなかったりする。
最初の10回くらいはぜんぜん見当違いのところをまとめてしまうが、10回を超えた頃からまとめ方が上手くなってくる。
20回もやると「う~ん」とうなるほどに上手くなってきて、自然と模試の偏差値もグンと上がってくる。
成績があがってくるのは国語だけではなく、長文問題がある数学や理科でも上がってくるから面白い。
●「書く力」
書く力を鍛えるのはなんと言っても作文。
作文を苦手と思っている子がなんと多いことか。
「うちの子供も作文が苦手で・・・」と思っているお母さん。
「わたしが一生懸命教えてあげているのにぜんぜんダメなんです。
苦手意識を持っているようで・・・」と思っていませんか?
実はその「作文の苦手意識」を植え付けているのはお母さん自身だったりすると高濱先生は指摘している。
子供が書いているそばからうるさく口を出していませんか?
できた作文を読んでここがダメ、あそこがダメと言っていませんか?
そんなこと言ったら100%作文が大っ嫌いになってしまいます。
保証します!
子供が「嫌いな」作文を書くだけでもすごいことと思わなくっちゃ。
「よく書いたねぇ」でいいんです。
塾では作文を書かせるときに使うのが「シンプルマッピング」だ。
学力検査のPISAで世界一になったフィンランドでは「カルタ」、会社では「マインドマップ」と呼ばれたりしているが、これを上手く使えば作文は上手くなる。
実はこれは大学受験などの小論文作成でも使われたりしているので今のうちに身に付けておけば絶対役に立つ!
私はを本を読んだり、新しいことを考えたりするときにこの「シンプルマッピング」を使っている。
これって使いこなせるようになったらすごい武器ですよ。
これを使って書いたうちの生徒が神奈川の作文コンクールで入賞したので、折り紙つきの方法。
この「シンプルマッピング」についていはまたブログで触れます。
これらの「読む力」「書く力」は中学校のうちに苦手意識を取ってあげないと私みたいに社会人になってから苦労しますので早めに手を打ってあげたいですね。